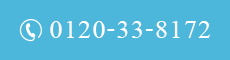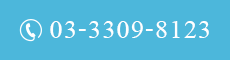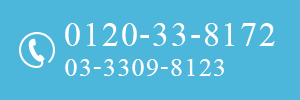みなさんこんにちは☼
お天気が変わりやすかった
8月も残り僅かとなりましたが
いかがお過ごしでしょうか?
今回は歯ぎしりについてです。
私自身も歯ぎしりや食いしばりがあり
一時期悩まされていました。
顎が痛い開かない
歯がしみる
ほっぺを噛んでいる
頭や肩も痛い気がする
なんてことありませんか?
それはもしかしたら
疲れや虫歯などではなく
歯ぎしりや食いしばりの
可能性もあるかもしれません。
歯ぎしりにはいろいろなタイプがありますが
成人の方の歯の噛む力は
およそ30〜70kgと言われています。
寝てる間や何かに取り組んでいる際
無意識に歯に負担がかかり
痛みや揺れの原因になっているかもしれません。
普段歯ぎしりはしないという方も
口腔内を拝見した際に
歯がすり減ってしまっている
ケースも少なくありません。
実際に自分もしみてしまったり
一時期は口が開かなくご飯を食べるのも
困難なことがありました。
そして成人の方だけではなく
ちいさなお子様も歯ぎしりや食いしばりを
している事もあります。
治療法は様々ですので
歯ぎしりや食いしばりだけではなく
お口のトラブルで「もしかしたら…」
と思うことがありましたらご相談お待ちしております。
世田谷区 千歳烏山 浜岡歯科クリニック
歯科助手 大場が担当致しました。